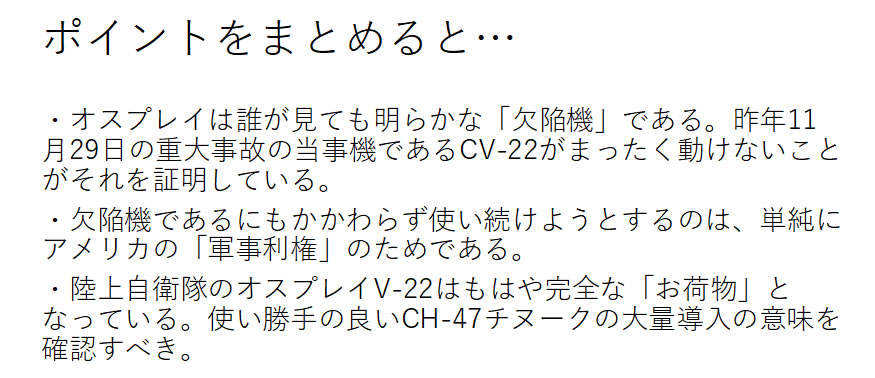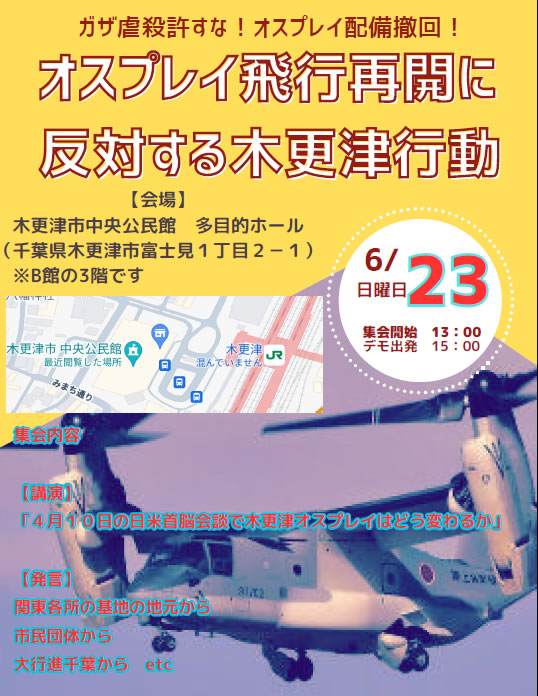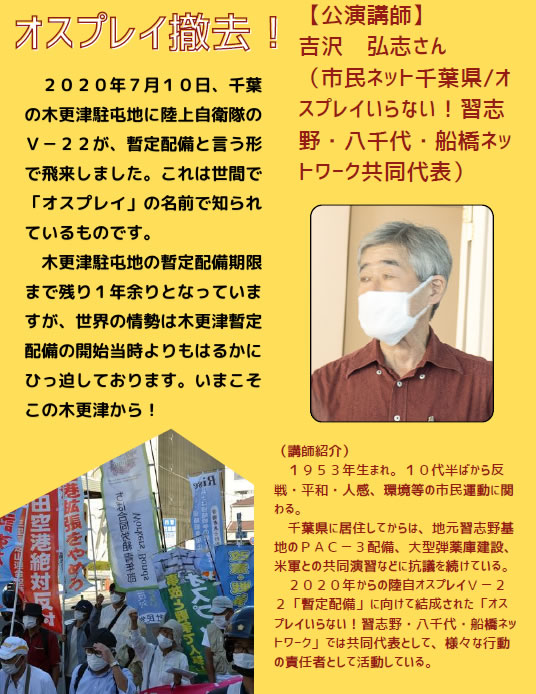熊谷俊人千葉県知事は幕張メッセを 「死の商人」に使わせるな!
主催:改憲・戦争阻止!大行進千葉 http://mayday.sub.jp/kaiken.no/
X( 旧Twitter): @DaikousinC
日時:9月29日(日)
(正午~ 海浜幕張駅前にてリレートーク、13時~ 幕張メッセ~ZOZOマリンスタジアム周辺でのデモ行進)
来年5月21日~23日、幕張メッセ(千葉市美浜区)で「武器見本市 DSEI JAPAN 2025」が行われようとしています。武器を生産・販売している軍事企
業(「死の商人」)が世界から281社、現在パレスチナ人民を大虐殺しているイスラエルからも15社が参加しようとしています。
自社の兵器がいかに民衆を殺傷することに優れているかを売り込み、売買契約を結び、人殺しの兵器で金もうけするのです。実際、幕張メッセでの武器見本市で、イスラエルの軍事企業が自社の兵器がパレスチナ人民虐殺など「戦場で実証済み」と言ってセールスしてきました。それを千葉県の公共施設たる幕張メッセで行わせるなど、どうして許せるでしょうか。
私たちは戦争のための武器見本市に絶対反対です。熊谷俊人千葉県知事は武器見本市に幕張メッセを貸さないでください!
昨年の10月7日以来、イスラエルによるパレスチナ人民大虐殺で、4万人ちかくのパレスチナ人民が虐殺されました。イスラエルは、パレスチナ人民虐殺のために、攻撃型ドローンなどの最新兵器を投入し、AI(人口知能)を使った殺人兵器を使用しています。AIがハマス(イスラム抵抗運動)の戦闘員だと判断したら、直ちに攻撃するということがおこなわれています。攻撃対象が病院、学校、難民キャンプにいても、まわりに子どもや女性がいようとお構いなしに、無差別に攻撃を加えています。その結果、パレスチナの死傷者の大多数が子どもや女性です。
武器見本市でイスラエルは、こうした無差別の人殺し兵器を「優れた兵器」として売り込むのです。日本の防衛省もイスラエルからドローン兵器を購入しようとしています。戦争のための武器見本市に絶対反対の声をあげましょう!
4月に行われた日米首脳会談・共同宣言で、日本の自衛隊と米軍の指揮命令機能の一体化が確認され、アメリカの戦闘機や軍艦などを日本で修理することや武器の生産でも共同で行うことが確認されました。日本政府は、5年間で軍事費の倍増を決め、年間10兆円の軍事費(防衛費)をめざし、国内の軍事産業の育成のために多額の税金を投入することを決めました。
企業と軍事関係の契約する際に8%ほどに設定していた利益率を、2023年度からは最高15%に引き上げました。その結果、三菱重工業は軍事関係の受注が3・4倍の1兆4781億円になっています。自衛隊と軍事企業はますます癒着が進み、裏金問題や接待問題などが明らかになっています。
日本とアメリカは、対中国の戦争を決断し、奄美大島・沖縄本島・宮古島・石垣島・与那国島などに自衛隊の警備部隊やミサイル部隊が次々と配置され、軍事要塞化が進んでいます。政府や経済界は、「安全保障と経済成長の好循環」を掲げ、軍事産業の育成と武器の生産や海外輸出で金もうけし、中国との戦争を構える戦争国家へと大転換しようとしています。幕張メッセで行われる武器見本市も、防衛省・防衛装備庁・経済産業省などが誘致を進め、政府と経済界が積極的に開催を後押ししています。
2023年の世界の軍事費は総額2兆2千億ドル(約329兆円)で前年比9%増。世界中で競い合うように武器の生産が進んでいます。しかし、ウクライナ戦争やパレスチナでの大虐殺を見れば、戦争で殺されるのは子どもや女性も含む民衆です。戦争で金もうけしているのは一握りの軍事企業です。そして、労働者人民には防衛費増大のための大増税や社会保障や教育予算の切り捨てが襲いかかります。
ウクライナ戦争絶対反対! パレスチナ人民大虐殺をいますぐ辞めろ! 日本とアメリカは中国に対して戦争するな!
幕張メッセを武器見本市に使わせないための千葉県知事あてのオンライン署名も行っています。幕張デモとオンライン署名へのご協力をお願いします。
千葉県知事宛てのオンライン署名にご協力を
(下記QRコードからキャンペーンページを開くことができます)
オンライン署名(Change.org)の仕方
1 QRコードからのChange.org のページを開く
2 氏名やお住いの市や区(すべて入れなくてもOK)、 郵便番号、メールアドレスを入力する
3「今すぐ賛同」をクリック
4 ブラウザを閉じる
5 受信メールをチェックする
6 送られてきたメール本文の赤いボタンをクリックする
7 署名完了
※キャンペーン広告への金銭的な支援を求められますが、広告を支援しなくても署名は成立しています
(署名集約先)とめよう戦争への道









 長時間検査クアッドドローン(飛行時間100分)
長時間検査クアッドドローン(飛行時間100分)
)
)
)

)

 地
地
)
 航空通信および衛星追跡海上および地上局ソリューションを提供する世界有数のプロバイダー ステディコプター 高度な無人ロボット ヘリコプター (RUAV) の大手プロバイダー
航空通信および衛星追跡海上および地上局ソリューションを提供する世界有数のプロバイダー ステディコプター 高度な無人ロボット ヘリコプター (RUAV) の大手プロバイダー